こういう時に子どもたちと話し合うこと (5年前と変わったところ、変わらないところ)
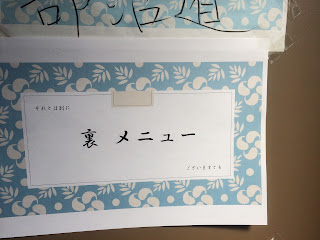
20年後の未来のために、新・青山Fプレップスクールです。 ぼく自身、20代の頃に熊本で仕事をさせていただいて、 また個人的にもお世話になっている方もいらっしゃるので、 今起こっている災害については、かなり身近に感じております。 仕事が忙しくて、熊本城も、阿蘇山も行っておりませんが、 空港へ向かう途中の益城町は、東京から出張で行っている身からは、 なんとものどかで、特に何もないけれど(すみません、知らないだけかも) だからこそ、いいところだなと思っておりました。 被害に遭われた方、今も大変な苦労をされている方、 たくさんの方々の何らかの力になればと思っております。 ここ数日、子どもたちと接していて、 5年前の東北の地震の時と比べて、ぼくなりに感じること。 第一は、 ちょっと距離があるんだろうな、ということです。 5年前は東京もかなり揺れましたし、余震も長く続きました。 食料品なども、一気に小売店から姿を消しました。 福島のことで、東京も停電になったり、また避難したほうがいいのか、 子どもなりに、感じるものが多かったと思います。 5年を経て、 幼稚園・保育園児だった子たちは、今は小学生。 小学生は、中高生。 中高生は、大学生になっています。 あの時と比べて、「遠くで起こっていること」。 直接自分たちの生活に、少なくとも今のところ影響のない子どもたちにとっては、 情報源は主にテレビに限られ、 それに対しても、ちょっと「慣れ」のようなものがあるのだと思います。 ○ 「専門家」と呼ばれる人たちが語ること ○ ピンポイントで届かない行政の対応 ○ 原発に関する平行線のやりとり ○ 報道に対するあれやこれや ○ 自粛しろ、いや自粛しても意味がない ==================== 先週から、できるだけちょっとでも、授業を延長してお話していること。 【関心を持っていろいろな情報に接し、また、いろいろな人と話し合ってね】 1. 災害対策という観点 人間がわかっていること (わかっていると思っていること) なんて、 ...